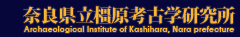第1弾
下ツ道とその周辺の遺跡
―郡山下ツ道ジャンクションの発掘調査成果を中心として―

当研究所ではその建設にともなって平成14年から平成27年にかけて発掘調査をおこない、令和2年に報告書を刊行しました。
その調査では、奈良盆地を南北に走る古代の直線道路である「下ッ道」の一部をはじめとして、各時代の遺構・遺物がみつかりました。今回はこれらの調査を中心に取り上げ、下ッ道周辺の調査成果を時代別に紹介します。
縄文時代
縄文時代は、狩猟・漁撈と植物採集が食料を獲得する主な手段だった時代と考えられています。郡山下ツ道ジャンクション周辺の発掘調査においては、奈良盆地低地部におけるこの時代の人々の生活のようすをうかがわせる資料をまとまって確認することができました。発掘調査の結果、縄文時代後期と晩期を中心とする時期にこの一帯は、小規模な河川(流路)が浸食と堆積をくり返すような場所であったことがわかりました。流路の中かからは大小の自然木が多く出土しています。土壌の中に残っていた花粉を分析したところ、流路の周辺には落葉広葉樹を主体とする小規模な林が存在したことがわかりました。

発掘された流路

貯蔵穴

クリの集積

縄文時代後期の土器

土偶
弥生・古墳時代
弥生時代の人々が死者を葬るためにつくった墓は、地域ごとに異なる特徴をもつことがわかっています。近畿地方で一般的であった墓の形態は、四角形に溝を掘り、その内側に土を盛り上げた低い墳丘の上に木棺等をおさめるもので、方形周溝墓と呼ばれています。郡山下ッ道ジャンクションの調査では、弥生時代中期を中心とする、多数の方形周溝墓を確認することができました。方形周溝墓はあわせて101基にのぼり、近畿地方でも屈指の大規模方形周溝墓群です。ほとんどの方形周溝墓は後世に上部が削られており、埋葬施設は残っていません。

方形周溝墓の例(JI区ST02)

初期の方形周溝墓から出土した土器

須恵器の出土状況

まとまってみつかった須恵器
古代
古代の奈良盆地には複数の正方位の直線道路がつくられました。南北方向のものは上ッ道、中ッ道、下ッ道の3つが等間隔に平行して走るもので、7世紀初め頃に成立したと考えられています。最も西側の下ッ道は、平城京内で中央を走る朱雀大路として踏襲されているほか、奈良盆地の条里地割を東西に分ける基準になっていることなどから、奈良盆地内の交通の基幹となる道路であったと考えられます。今回の調査箇所にはこの下ッ道が走る地点が含まれ、発掘調査においてもその遺構が確認することができました。そして「郡山下ッ道ジャンクション」という名称の中にも取り入れられました。
最も顕著な遺構は、下ッ道東側溝であるSD2001で、幅6~12メートル、深さ1.4~2メートルの大規模な溝で、内部には橋脚とみられる柱や、水をせき止めるしがらみ状の遺構もみつかっています。また溝の中から出土した遺物には、土馬や斎串などの祭祀にかかわるもののほか、ウマやウシなどの骨も認められます。この溝は、出土した遺物から奈良時代の8世紀中頃から9世紀前半頃まで機能していたと考えられます。

下ッ道東側溝SD2001(南から、溝の左側が下ッ道の路面)

下ッ道東側溝SD2001杭列検出状況

奈良三彩

奈良時代の瓦
中近世
郡山下ッ道ジャンクションの発掘調査成果によると、下ッ道が廃絶した後の中世の時期には、所々で遺構や遺物が確認される程度で、人間の生活痕跡は希薄になっていくことがわかりました。この時期以降、周辺には条里地割に基づいた耕作地が広がっていたと考えられます。下ッ道に近接し、郡山下ッ道ジャンクションの約1キロメートル南にある中町西遺跡では、京奈和自動車道建設にともなう発掘調査で、10世紀から12世紀を中心とする時期に営まれた掘立柱建物や井戸などの生活遺構がみつかっています。ここでは12世紀頃につくられた濠による区画がみとめられ、居館跡と考えられます。

中町西遺跡でみつかった井戸


菅田遺跡でみつかった濠